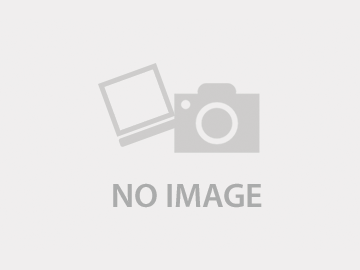うなぎの蒲焼きについて調べていると、「うなぎ 関東 関西の違い」というテーマは多くの方が興味を持つポイントではないでしょうか。
さばき方が「背開き」か「腹開き」かによる「見た目」の違いや、その「見分け方」、そして調理法が生み出す「味の違い」は一体どこにあるのでしょう。
また、それぞれの地域で愛される「タレ」の個性や、時折耳にする「関東風 まずい」という話の真相、そして最終的に自分は「どっちが好き」かを見極めたい、そんな思いもあるかもしれません。
この記事では、「関西」と「関東」のうなぎ文化を深掘りします。
さらに、独自の食文化を持つ「名古屋」や、うなぎの有名処である「浜松」における「関東」「関西」スタイルのうなぎ事情、そして気になる文化の「境目」はどこなのか。
はたまた「東京」でも美味しい「関西風」うなぎは楽しめるのか?まで、あなたの疑問を解消できるよう詳しく解説していきます。
- うなぎの関東風と関西風における調理法(さばき方・蒸し・焼き方)の具体的な違い
- 調理法に起因する食感、味わい、そしてタレの傾向といった風味の違い
- 関東・関西だけでなく名古屋も含めた地域ごとのうなぎの特徴と文化的な境目
- 見た目の見分け方や味の好みの判断基準、関東風に関する一般的なイメージの背景
Contents
うなぎ関東風と関西風その違いを徹底比較
| 特徴 | 関東風 | 関西風 |
| 開き方 | 背開き | 腹開き |
| 調理法 | 蒸してから焼く | 蒸さずに直火で焼く |
| 食感 | ふんわり柔らかい | 皮がパリッと香ばしく、身はしっかり |
| タレ | あっさり系・さらっとした甘辛 | 濃厚で甘み・コクが強い |
| 主な地域 | 東京・埼玉・千葉など関東地方 | 大阪・京都・名古屋など関西地方 |
| 代表的な料理 | うな重・うな丼 | ひつまぶし、うな重 |
関東風と関西風のうなぎには、さばき方から焼き方、味わいを左右するタレに至るまで、知っておきたい多くの違いが存在します。ここでは、それぞれの基本的な特徴を詳しく見ていきましょう。
開き方に注目!背開きと腹開きの見た目の違い
うなぎの関東風と関西風では、まず調理の初期段階である「開き方」に見た目の違いが現れます。これは、うなぎのどの部分から包丁を入れるかという根本的な手法の違いによるものです。
関東風で主流の「背開き」は、うなぎの背中側から包丁を入れて開いていきます。そのため、蒲焼きになった際、身の中心線が背側にあり、お腹側の皮が繋がったような形になるのが特徴です。
一方、関西風で一般的な「腹開き」は、うなぎのお腹側、つまり内臓がある側から包丁を入れて開きます。こちらは、開いた際に身が左右対称に近い形で広がりやすい見た目となる傾向があります。
ただ、蒲焼きとして最終的に食卓へ運ばれる状態では、タレが塗られ、串も抜かれていることがほとんどでしょう。そうなると、一見してどちらの開き方であるかを見分けるのは、慣れていないと少々難しいかもしれません。
うなぎの背開きと腹開きの見分け方は?
うなぎの背開きと腹開きを確実に見分けるには、調理前の開かれた状態、特に切り口の位置を確認するのが最も分かりやすい方法です。なぜなら、お店で提供される蒲焼きの状態では、調理法や盛り付け方によって判断がつきにくくなるためです。
具体的に申しますと、背開きのうなぎは、その名の通り背中側に直線的な切り口が入っています。お腹側の身は比較的連続して見えることでしょう。対して腹開きのうなぎは、お腹の中心に切り口があり、内臓を取り除いた跡がより明確に確認できることが多いです。
飲食店で蒲焼きとして出された場合、串の種類もある程度のヒントにはなり得ます。しかし、これらはあくまで傾向であり、絶対的な見分け方とは言えません。もし気になるようでしたら、お店の方に尋ねてみるのが一番確実な方法と言えるでしょう。
伝統的には関東風が竹串、関西風が金串や頭の有無(関東風は通常落とし、関西風は付けたまま焼くことが多い)提供時に落とす場合もあります)
調理法が決め手!背開き・腹開きの味の違いとは
うなぎの「背開き」と「腹開き」という、さばき方そのものが味に直接的な大きな違いを生むわけではありません。味わいの主な違いは、実はその後の調理工程、特に「蒸し」の工程の有無によって大きく左右されるのです。
関東風のうなぎは、多くの場合背開きにされた後、白焼きにしてから一度「蒸す」という工程が入ります。この蒸しによって余分な脂が落ち、身が非常にふっくらと柔らかく仕上がります。口の中でとろけるような食感が特徴で、皮も柔らかくなる傾向にあります。
一方、関西風のうなぎは、腹開きにしてから「蒸さずに」そのままタレをつけて焼き上げる「地焼き」という手法が一般的です。蒸す工程がないため、うなぎ本来の脂の旨味が残りやすく、皮はパリッと香ばしく焼き上がります。身も関東風に比べるとしっかりとした歯ごたえや弾力が感じられるでしょう。このように、開き方と伝統的に結びついている調理法が、最終的な味と食感の違いを生み出しているのです。
関東風と関西風うなぎのタレを比較
関東風と関西風のうなぎでは、蒲焼きの味わいを決定づける重要な要素である「タレ」にも、それぞれ特徴的な傾向が見受けられます。これは、各々の調理法で仕上げられたうなぎの個性に合わせて、タレもまた独自の進化を遂げてきたからだと考えられます。
関東風のうなぎに使われるタレは、比較的あっさりとしていて、粘度が低くサラッとした口当たりのものが多いと言われています。醤油とみりんをベースにしながらも、甘さは控えめで、キレのあるすっきりとした味わいが特徴です。このタレが、蒸されてふんわりと柔らかくなったうなぎの身によく馴染みます。
対して関西風のうなぎのタレは、濃厚でとろみがあり、しっかりとした甘みとコクを感じさせるタイプが主流です。中にはたまり醤油を用いたり、砂糖を多めに配合したりするお店もあり、直火で香ばしく焼き上げられた脂の乗ったうなぎの力強い風味に負けない、存在感のある味わいとなっています。ただ、これらはあくまで一般的な傾向であり、お店ごとに長年受け継がれてきた秘伝のレシピがありますので、その多様性を楽しむのも一興です。
関東風うなぎはまずい?その理由を解説
「関東風うなぎはまずい」という声を聞くことがあるかもしれませんが、これは決して関東風うなぎの品質が劣っているという意味ではありません。多くの場合、個人の味の好みや、期待するうなぎの食感とのミスマッチから生じる感想と言えるでしょう。
その主な理由として、関東風うなぎ最大の特徴である「蒸し」の工程が挙げられます。蒸すことによって生まれるふんわりと柔らかい食感、そして比較的あっさりとした上品な味わいが、関西風のうなぎに慣れ親しんだ方にとっては、少々物足りなく感じられることがあるのです。例えば、パリッとした皮の香ばしさや、しっかりとした身の歯ごたえ、濃厚なタレの味わいを期待している場合、関東風の繊細な食感や風味は「思っていたのと違う」という印象に繋がりやすいのかもしれません。
しかし、逆に考えれば、このふっくらとした口どけの良さや、うなぎ本来の味を活かした優しい味わいこそが関東風の魅力です。余分な脂が程よく落ちているため、たくさん食べてももたれにくいと感じる方もいらっしゃるでしょう。関東風、関西風、どちらのスタイルも日本のうなぎ文化を代表する調理法であり、優劣ではなく、それぞれの個性を理解し、自分の好みに合わせて選ぶのが美味しくいただくための秘訣です。
うなぎ関東風と関西風など地域差と選び方
うなぎの調理法や味わいは、地域によっても特色があり、食文化としての奥深さを感じさせます。その境界線や、代表的な都市でのうなぎ事情、お店選びのヒントについてご紹介します。
関東と関西うなぎ文化の境目はどこ?
うなぎの調理法における関東風と関西風、この二つの食文化がどこで分かれるのか、その境目について興味を持つ方もいらっしゃるでしょう。一般的には、静岡県の浜松市周辺から長野県の諏訪湖へ至る天竜川沿い、あるいは愛知県と静岡県の県境あたりが、その境界線とされています。
このような地域が境目とされる背景には、地理的に東西の文化が接触し、影響しあう場所であったことが考えられます。このラインを大まかな目安として、東側では背開きにしてから蒸す関東風のうなぎが、西側では腹開きにして蒸さずに焼き上げる関西風のうなぎが多く見られる傾向にあります。
特に、静岡県浜松市などでは、関東風と関西風、両方のスタイルのうなぎを提供するお店が混在しており、まさに食文化の移行地帯であることを物語っています。もちろん、現代では物流も発達し、料理人の交流も盛んですから、この境界線も絶対的なものではなくなりつつあります。しかし、日本の食文化の多様性を示す一つの目安として、非常に興味深い点と言えるでしょう。
浜松のうなぎは関東風?それとも関西風?
静岡県浜松市はうなぎの産地として名高いですが、その調理法が関東風なのか関西風なのか、一概にどちらか一方に定めることはできません。むしろ、浜松のうなぎ文化は、関東風と関西風の両方の調理法が共存し、お店によってそれぞれ特色あるうなぎが提供されている点に大きな特徴があります。
前述の通り、浜松は地理的に関東と関西のうなぎ文化が出会う境界線上に位置しています。そのため、東西双方の食文化の影響を受けながら、独自のうなぎ料理を発展させてきました。市内には、伝統的な背開きで蒸しを加えてふっくら仕上げる関東風の老舗もあれば、腹開きで蒸さずに炭火で香ばしく焼き上げる関西風の技法を守るお店も点在しているのです。
このような背景があるため、浜松を訪れた際には、関東風と関西風のうなぎを食べ比べてみるという、他ではなかなかできない楽しみ方ができます。お店を選ぶ際には、どちらの調理法で提供されているのかを事前に調べてみたり、お店の方に尋ねてみたりすると、より自分の好みに合ったうなぎに出会えるでしょう。
関西・関東・名古屋のうなぎの特徴
これまで主に関東風と関西風のうなぎの違いについて触れてきましたが、日本のうなぎ料理はそれだけではありません。愛知県名古屋市を中心とする中京地方にも、また独自の発展を遂げたうなぎ文化が存在します。
関東風のうなぎは、繰り返しになりますが、背開きにして一度蒸してから焼き上げることで、ふんわりと柔らかい食感と、比較的あっさりとしたタレが特徴です。一方、関西風は腹開きにし、蒸さずに直火で焼き上げるため、皮はパリッと香ばしく、身はしっかりとした歯ごたえがあり、濃厚なタレで味わうのが一般的です。
そして名古屋を中心とする中京地方のうなぎは、調理法としては関西風に近く、腹開きで蒸さずに地焼きします。しかし、その焼き方はより高温で徹底的に焼き込むことで、表面はさらにカリッと、中はジューシーに仕上げる傾向が強いと言えるでしょう。タレも、たまり醤油などを用いた非常に濃厚で甘辛いものが好まれます。この地域で生まれた代表的なうなぎ料理が、細かく刻んだ蒲焼きをご飯にまぶし、薬味やお出汁で味の変化を楽しむ「ひつまぶし」です。このように、それぞれの地域で好まれる食感や味わいに合わせ、独自の調理技術や食文化が育まれてきました。
東京でも食べられる?関西風うなぎのお店
関東地方の中心である東京においては、やはり関東風のうなぎを提供するお店が多数派です。しかし、「東京では関西風のうなぎは食べられないのだろうか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。結論から申しますと、数は限られるものの、東京でも本格的な関西風のうなぎを味わうことは可能です。
近年では食文化の多様化が進み、また、関西出身の方や関西風の味わいを好む方々の需要に応える形で、東京にも関西風の調理法を用いたうなぎ専門店が登場してきています。これらの店では、腹開きにしたうなぎを蒸さずに炭火などでじっくりと焼き上げ、皮はパリッと香ばしく、身はしっかりとした食感という関西風ならではの魅力を堪能できます。
もし東京で関西風のうなぎを探すのであれば、インターネットのお店情報サイトなどで「関西風」「地焼き」「腹開き」といったキーワードで検索してみるのが有効な手段です。また、お店によっては予約時に焼き方について尋ねてみるのも良いでしょう。普段慣れ親しんだ関東風とはひと味違ううなぎの美味しさに、きっと出会えるはずです。
まとめ
「うなぎ 関東 関西の違い」は奥深く、さばき方(背開き/腹開き)、調理法(蒸す/蒸さない地焼き)、タレの風味まで多岐にわたります。関東風はふんわり柔らか、関西風は皮がパリッと香ばしく、食感も対照的です。名古屋のひつまぶしのような地域独自の食文化や、浜松のように両方のスタイルが混在する地域もあります。これらの違いを知ることで、より自分好みのうなぎを見つけやすくなるでしょう。